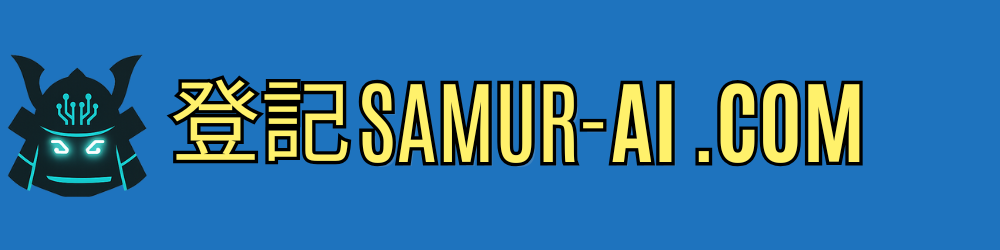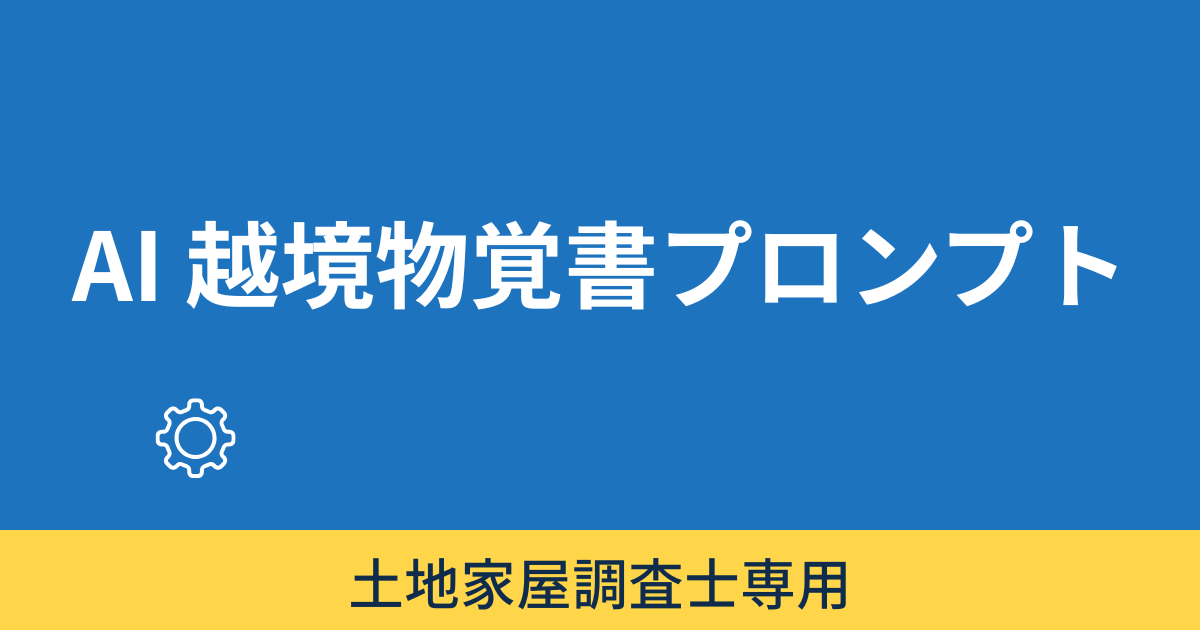境界確定や測量業務に忙殺される中、「越境物覚書」の作成に時間を取られていませんか?
この記事では、まずすぐに使える覚書の基本ひな形を提供し、書類作成の第一歩をサポートします。
さらに、ひな形利用後も残る「名前や地番の繰り返し入力」や「転記ミスのチェック」といった面倒な作業を、AIがいかに早く、正確に、そして手軽に解決できるかを具体的に解説します。
土地家屋調査士業務の手入力の工数をゼロにし、コア業務に集中するための、最新の効率化手法をご覧ください。
1. 冒頭:ひな形の提示と業務効率化
越境物覚書は、隣接者との合意を明確にする重要な文書であり、その作成には正確性が求められます。その都度ゼロから作成することは、多大な時間と労力を要します。
本記事では、書類作成の手間を軽減し、業務効率化を図るために、すぐに利用可能な越境物覚書の基本ひな形を提供します。まずはこのひな形をご活用ください。
越境物覚書 基本ひな形(Markdown/テキスト版)
| 越境物覚書 |
|---|
| 令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
覚書当事者
【甲】
住所:〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
氏名:甲(所有者)
【乙】
住所:〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
氏名:乙(隣接者)
甲と乙は、下記の通り覚書を取り交わす。
記
- 対象地
- 甲所有地:〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
- 乙所有地:〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
- 越境物の特定
- 越境物の種類:【例:ブロック塀、軒先、樹木等】
- 越境面積/長さ:【測量図に基づいて具体的に記載】
- 越境の状況:甲所有の〇〇が、乙所有地に〇〇メートル越境していることを確認した。
- 合意事項
- 越境物については、【例:将来的に乙の敷地内で工事を行う際に、甲の費用負担で撤去する】 まで現状のまま存置を認める。
- 甲は越境物の存置に関し、乙に対し今後一切の異議を申し立てない。
- 特記事項
- 本覚書は、甲及び乙のそれぞれの承継人に対しても効力を有するものとする。
上記合意の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
| 署名押印欄 |
|---|
| 甲:甲(所有者) [印] |
| 乙:乙(隣接者) [印] |
2. ひな形の基本的な使い方:まずは手作業で効率化
このひな形は、確定測量業務時に発覚した越境物について、地主(依頼者)と隣地所有者で取り交わすべき、必要な項目を満たしています。
まずはこのままお使いいただき、必要な項目を埋めていくだけで、すぐに基本的な覚書が完成します。
- 手順1:日付、当事者情報、地番:まずは「〇〇」「△△」のプレースホルダーを案件情報に置き換えます。
- 手順2:越境物の特定:種類、面積、そして具体的な状況(どこから、どのくらい)を正確に記載します。
- 手順3:合意事項:「いつ、誰が、どうする」という将来の取り扱い(例:撤去、存置)について明確に記載します。
この作業は慣れた方であればすぐですが、「この氏名、また別の書類(境界確認書など)にも書くのか…」と、手入力の手間を感じる瞬間があるかもしれません。
3. AIを使うメリット:手間とミスを劇的に削減
書類作成で一番時間がかかるのは、物件や関係者ごとの「情報の差し替え」と「転記ミスのチェック」ではないでしょうか?
調査士業務では、同じ名前や住所を何度も、何枚もの書類に手入力する機会が非常に多いです。
ここでAI(生成AI)の出番です。
AIを活用すれば、お隣さんや地主さんの名前、地番といった情報を、最初に一度だけ入力しておくだけで、この覚書を含めた関連するすべての書類に自動で反映させることが可能になります。
| 従来の作業 | AIを導入した場合 |
|---|---|
| 書類ごとに氏名・地番を手入力。 | 基本情報を一度だけAIにインプット。 |
| 転記ミスがないか、人の目で全件チェック。 | AIが自動で差し込み、チェック工数が激減。 |
| 書類作成に時間がかかり、現場に出る時間が削られる。 | 手間が激減し、転記ミスがゼロに近づく。 そして、現場作業の時間が創出できる! |
このように、AIを使うことで作業効率が向上し、転記ミスのリスクも大幅に軽減できるでしょう。
そうすれば、面倒な手入力で取られていた時間から解放され、現場や調査といった本来の業務に充てられるようになります。
4. 具体的な手順:AIツールの簡単な活用イメージ
「AIなんて大々的なシステム導入が必要で難しそう」と感じるかもしれませんが、ご安心ください。
手順は非常にシンプルです。
最近のAIツール(例:高度な文書生成機能を持つAIチャットや、連携可能なテンプレートサービス)は、以下のような手順で、すぐに業務に組み込めます。
- AIツールを立ち上げる: PCからAIチャットサービス等にアクセスします。
- 基本情報を入力: 「今回の案件の甲(所有者)は〇〇様、乙(隣接者)は△△様。甲所有地はA地番、乙所有地はB地番。越境物はブロック塀で、将来乙の工事時に撤去」と、基本情報を一度だけ入力します。
- ひな形を読み込ませる: 上記のひな形をAIに読み込ませます。
- 指示を出す:
AIの能力を最大限に引き出すためには、正確かつ詳細な「指示文(プロンプト)」の作成が必要です。
単なる「覚書を作成して」という指示だけでは不十分なケースもあり、プロンプト作成自体が難しいと感じるかもしれません。
では、このプロンプト(指示分)を作成するにはどうすればよいでしょう?
実は、「プロンプトもAIに作らせる」ことが可能です。
では、その方法を次の章でご紹介します。
登記サムライドットコムの専用プロンプトメーカーを活用する
この難しいプロンプト作成の手間を完全に排除するのが、登記サムライドットコムが提供する「越境物覚書作成プロンプトメーカー」です。このツールは、必要な情報をフォームに入力するだけで、複雑な条件や文書構成指示を含んだChatGPTへ貼り付け可能な、完全な覚書作成用プロンプトが自動生成されます。
そうすれば、複雑な指示(プロンプト)は自分で考えなくても済み、手軽にAIを活用した文書作成を始めることができます。
カスタマイズされた書類が完成: AIが自動で氏名や地番、合意事項を埋め込み、クリック数回で案件専用の覚書が完成します。
AIツールを活用することで、面倒な転記作業から解放され、業務効率が飛躍的に向上します。
5. AIの留意点:生成内容の確実性を担保するための最終確認
ただし、便利なAIにも注意点はあります。
AIは非常に優秀ですが、まれに「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれる、もっともらしいが事実と異なる情報を生成することがあります。
例えば、文脈から不適切な言葉を選んでしまったり、合意事項が指示とわずかに異なってしまったりする可能性もゼロではありません。
重要な契約書類である「越境物覚書」では、情報の正確性が絶対です。
そのため、AIが作成した書類であっても、最終的な確認は必ず人の目で行っていただくことで、安心と確実な業務が両立できます。
AIはあくまで強力なアシスタントだと認識して活用しましょう。
6. まとめ:業務効率化の次のステップへ
まずは今回ご提供した基本のひな形を使って、書類作成業務を少しでも楽にしてください。
そして、次に書類作成に取りかかる際には、ほんの少しだけAIを取り入れてみることを検討してみましょう。
名前や地番の入力作業から解放されることで、ミスのない、より効率的な業務フローを手に入れられるはずです。
皆様の業務が、AIによってさらに快適になることを願っております。
「ウチの事務所でもAI導入しようか迷ってるけど、必要かどうか分からない」 そう思われた方は、まずはお気軽にご相談ください。(相談無料、オンライン対応) AI導入の要否、活用方針まで、御事務所の状況に合わせて具体的にアドバイスいたします。