
土地家屋調査士事務所の業務でAIを使うと言っても、実際にはイメージしにくいかもしれません。
本記事ではChatGPTなどのAIでできること、(まだ)できないことを解説して、実際に土地家屋調査士事務所でAIが使われている業務を紹介します。
分かりやすいように、今回はChatGPTに絞って解説します。
AI(ChatGPT)を導入してみようか考えている土地家屋調査士さんは、この記事を読めばChatGPTを実際に使うイメージができることでしょう。
ChatGPTでできること
具体的にChatGPTでできることは次のことです。
- 文章作成
- 文章の要約
- 翻訳
- 画像生成
それぞれについて解説します。
文章作成
文章作成は文字通り、希望する文章を作成することです。
「取引先の〇〇会社の田中部長からお中元をもらったので、丁寧なお礼状を作成してください。」
「新しい測量会社を設立したので、新会社設立の挨拶状を作成してください。」
などなど。
『誠意にかけるんじゃ?』と思われるかもしれませんが、書き方やひな型をネットで検索するのであれば同じことで、最終的には出てきた文章を自分らしく書き直せば良いでしょう。
また、極端なことを言えば謝罪文もできてしまいます。。。
「どうしても隣地が捕まらなくて確定測量が終わらない。先月から8回以上話に行っているけど、先代の地主さんに意地悪されたから協力したくないと言われて、承諾が得られない。
取引先・地主様には後1ヶ月以内には決着つけるので、納品を2週間遅らせて欲しいというお願いと謝罪の文章を作成してください。」
こういったものも可能で、ChatGPTの最も一般的な使い方です。
文章の要約
役所から届いた長文メール、同業から回ってきた10枚近いPDF資料、目を通す時間がないけど、読むだけは読んでおかないと後々困ることになる。
そんな時にはChatGPTに読ませて、「要点を教えてください。特に建物表題登記に関する内容は丁寧にお願いします。」と指示すれば、内容をまとめてくれます。
また、分からないところも「▲▲って、□□すれば問題ないってことですか?」と聞けば教えてくれます。
もちろん重要なところは自分の目で確認しなければなりませんが、ざっと内容を知るだけならこれで十分です。
翻訳
近年は隣地所有者が外国人というケースもあり、そんな時でもChatGPTが役立ちます。
不動産を購入される外国人であれば、通常は日本語での会話が可能です。
しかし、混み入った話だったり、相手の日本語が不安だったり、というケースであれば立会確認書に書いてある内容を翻訳してもらい、「※AIで翻訳しました」と注意書きを付けて渡すと相手も安心してサインしてくれるかもしれません。
画像生成
AIによる画像生成は著作権などこれから解決すべき問題も山積みではありますが、ちょっとした挿絵や事務所内で使うアイコンなどをサッと作って利用すると便利です。
このように、ChatGPTでは事務作業のサポートに大きく役立ちます。
ChatGPTが苦手・できないこと
一方、ChatGPTが苦手・できないことは感情を伴う交渉事(隣地立会)の代行、現場作業など現実世界で動くことで、次のようなものです。
【できないこと】
- 測量や杭入れなどの現場作業
- 隣地立会及び押印取得
- 役所との連絡
【現状、苦手なこと】
- 図面の作成(描写)
- 測量図の読み取り
それぞれ、次のような特徴があります。
測量や杭入れなどの現場作業
「AIに現場作業はできない」、これは説明も要らないと思いますが、AIではなくロボットが必要な作業です。
「AIが重機を捜査して無人で造成する動画」を見た方もいるかと思いますが、現時点では無人(自動)で測量作業を行うAI・ロボットは聞いたことがありません。
一方で3Dスキャナやドローン測量は従来の「点」だけではなく、「面」での測量も可能なほど進化しています。
私はどちらも使ったことがありますが、現況測量なんかには3Dスキャナ・ドローン測量はとても便利で、測量経験の少ない方でも「取り忘れが減る」という意味でもとても良いですね。
点群処理はハイスペックPCが必要なことと、値段がお高いのがネックですが・・・
このように、現実的に進んでいるのは3Dスキャナの方ですので、今後は「AIが測量する」というより、「3Dスキャナ(orドローン測量)+AI」での進化がメインとなるでしょう。
杭入れの自動化はまだ想像ができませんが、「座標を入れたらロケットのように杭を発射して打ち込む」とか何か革新的な技術ができることを祈りましょう。

隣地立会及び押印取得
隣地所有者への杭の説明、筆界確認書への押印などは当然ながら、今のAIには不可能です。
ロボットが説明しても信じてもらえるかどうか、隣地が怒っていたら、想像するだけで胃が痛くなりそうです。
ドラえもんのようなロボットなら愛嬌もあって良いかもしれませんが、それこそ22世紀の技術でしょうね。
境界確定の隣地立会においては、まだまだ数十年は調査士さんの力が必要だと思います。
AIが導入されたとしても調査士さんが動かすことになるので、結局隣地の方々との立会業務は無くならないでしょう。
役所との連絡
メールでのやり取りはAIでも可能なので、定型の事務連絡などは代替可能です。
ただ、「建物がギリギリということは分かりますが、道路幅員4mは確保してくれますか?」といった交渉ごとになるとAIでは判断できないため、代替できない作業と言えます。
この辺りは許容範囲や定型内容を学習させれば技術的には実現できるかもしれません。
図面の作成(描写)
2025年現在の技術では「AIでCAD図面を描く」ことはできません。
これは技術的な問題もありますが、そもそも近年全盛のAIは大規模言語モデル(LLM)といって、いわゆる「チャット」での言葉のやり取りです。
そのため図面や画像とは相性が悪く、精密な数値・座標を取扱うCAD操作はできません。
AI画像生成はここ数年話題になっていますが、画像生成はCADとはシステムが違い、似たような画像を収集・再構成しており、「それっぽい」画像ができるだけです。
なお、ChatGPTを提供しているOPENAIAIとのコラボレーションを実現したCAD「ARES(アレス)」が存在します。
しかし、このARESはCADを自動操作してくれるわけではなく、「結線はどうやる?」「この土地は1区画●●㎡以上に分割すると何筆に分けられる?」といった質問にAIが答えてくれるというものです。
・・・CADを初めて使う方には良いかもしれませんが、「CAD作業もAIで代替!」にはまだほど遠い印象ですね。
測量図の読み取り
「AIで測量図の座標読み取りができたら便利なのに」
とChatGPTで試してみた方は多いのではないでしょうか?
うまくできた、全然よく分からない数字になった、ある程度できたけど結局全部チェックが必要で却って時間がかかった、色んな方がいらっしゃるでしょう。
AIは画像・PDFを読み取って解析することは可能ですが、OCRというデータ・文字を認識する技術を使っており、伝票や文章を想定しています。
そのため、地形図や求積図などの数値の読み取りは苦手で、地積測量図を読み取らせても「図面上の複数箇所(求積図、座標系、申請人、所在、地番)」をそれぞれ読み取ろうとすると失敗してしまいます。
そのため、AIによる測量図の座標化は難しいと言えます。
しかし、ChatGPTにはGPT-4Visionという機能が搭載されており、これはAIの目のような機能です。
この機能を使って地積測量図の読み方を学習させると、地積測量図の数値を読み取ってテキスト化することも可能です。
AIの杜さいたでは、この作業を事前に学習させ、測量図を読み取るカスタムGPTを開発しておりますので、次の章でご紹介いたします。
測量図を3分で座標化するカスタムGPT「きゅうせき君」
AIの杜さいたでは、土地家屋調査士向けの『測量図を3分で座標化するカスタムGPT』きゅうせき君、を販売しております。
カスタムGPTとはChatGPTの中に事前に知識やひな型を学習させておき、特定の作業を専門的に処理するAIのことです。
カスタムGPTを使えば事前に細かい設定などができるので、指示文(プロンプト)を考えず、スムーズに使うことができます。
このきゅうせき君は、事前に測量図の読み取り方法を学習しており、求積表・所在地番・座標系・基準点まで自動で読み取り、テキストデータで出力してくれます。
ポイントは下記の4点です。
- 作業は2ステップ、最短3分で座標をテキスト化
- 地積測量図・現況測量図の求積表を読み取る
- 求積表のある座標については検算を行う
- CADに貼り付けられるよう、「点名・X座標・Y座標」で出力してくれる
それぞれについて解説します。
作業は2ステップ、最短3分で座標をテキスト化
インターネットとChatGPTを使える環境であれば、お手元の測量図の座標を最短3分でテキスト化します。
手順は次のとおりです。
Step1.測量図(PDFファイル)を画像(JPEGファイル)化する
法務局の登記情報提供サービスから入手した地積測量図などであれば、下記サイトを使って画像(JPEG)データに変換します。
iLovePDF(PDFをJPEGに無料で変換してくれるサイト※外部リンク)
スキャナで読み取る場合には解像度を高く設定して、画像で読み取ります。
Step2.画像をきゅうせき君にアップロードする
画像変換したデータをカスタムGPT「きゅうせき君」にアップロードします。
後は数分でテキストデータとなって出力されます。
地積測量図・現況測量図の求積表を読み取る
きゅうせき君は、平成以降で座標求積表の図面(印字)であれば、ほぼすべて読み取ることが可能です。
地積測量図だけでなく現況測量図、確定測量図などにも対応しています。
ただし、下記のような図面は読み取りが難しく、手書きについてはほぼすべて失敗しました。
- 手書き:作成者ごとの字のクセがあり、読み取りが難しい
- 三斜図面:地形図に直接書き込まれた数値がどこの辺長を示しているかは読み取れません
- 印刷が薄い・荒い:印刷が薄い・荒いために文字判別が難しい場合も読み取りが難しい
求積表に面積が記載されている座標は検算を行う
読み取りの正確性を担保するために、面積が記載されている座標についてはプログラム(Python)を使って検算を行います。
読み取った座標から面積を求積し、アップロードされた測量図の面積と突合し、誤差が出た場合には読み取った文字に間違いがないか再チェックします。
フル桁での計算か小数点第2位までの計算かも判別できるので、ここで誤差がなければ、ほぼ間違いないでしょう。
ただし、点名、求積の無い基準点については計算によるチェックができないため、慎重に人間の目視によるチェックをお願いいたします。
点名・X座標・Y座標で出力
座標化したデータは「点名・X座標・Y座標」の様式でテキスト出力されます。
点名の数字の小さい順番に並びますが、並び替えも可能です。
また、地番ごとの座標出力も同時に行います。
出力データは次のようになります。
■ 地番 10-3
点名|X座標|Y座標|求積表の距離(m)|計算距離(m)
\K11|137.514|278.102|6.892|6.892
K10|130.623|278.198|3.450|3.450
K9 |130.672|281.648|3.000|3.000
K8 |127.672|281.690|4.500|4.500
K13|127.732|286.190|1.400|1.400
K15|126.332|286.185|10.868|10.868
K16|126.470|297.052|11.300|11.300
K5 |137.770|297.013|18.913|18.913
求積表の面積:191.4473600
検算した際の面積:191.4473600
面積誤差:0.0000000
地積:191.44 ㎡
きゅうせき君の注意点
以上のように、きゅうせき君を使えばこれまで測量図とにらめっこしながら、ポチポチと座標入力していた苦労をAIに代替させることが可能です。
しかし、下記のポイントについてhご注意ください。
・最終的には人間の目でチェックする
・手書き、三斜求積図面には非対応
・無料版ChatGPTの方は画像アップロード制限(1日2~3枚)があります
まとめ
土地家屋調査士事務所でAIを使う機会は挨拶状作成、翻訳、要約などの文章作成がメインで、アイコンや挿絵などの画像も作成ができます。
一方、測量や杭設置などの現場作業、隣地や取引先・役所との折衝にはまだAIの出番はほとんど無いと言えます。
しかし、ご紹介したきゅうせき君のようなカスタムGPTを活用すれば20分、30分とかかっていた作業が5分の1程度の時間に短縮できます!
1ヶ月に20枚あれば、2時間・3時間の短縮につながります。
AIを活用してこういった細かい効率化を行い、捻出された時間は営業活動、資格者しかできない立会い業務、自己投資の時間に使いましょう。
コメント一覧
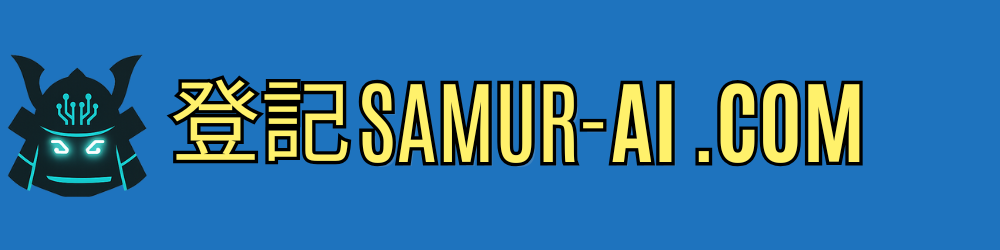

大阪府堺市の土地家屋調査士の伊藤哲哉と申します。
「きゅうせき君」に大変関心があり、購入ができればと考えています。
費用や購入方法等を教えていただけるでしょうか。
地積測量図の求積表をデータ変換した場合、文字化けなどで、修正が必要となることもあるのでしょうか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
伊藤哲哉様
コメントありがとうございます。「きゅうせき君」にご関心をお寄せいただき光栄です。
ご質問の件、要点を回答いたします。
年額6,600円(税込/月換算550円)です。まずは「メルマガ登録」にて1ヶ月間の無料お試しをご利用いただき、ご納得された上で購入をご案内しております(ChatGPT無料版で動作します)。
自動検算機能があるため精度は高く(約99%)、エクセル貼付用データのため文字化けもありません。ただし、画質の荒い図面(数字の潰れ)や、検算できない基準点情報などは、最終的な目視チェックをお願いしております。
まずはぜひ、無料版で使用感をお試しください。詳細やご相談は下記よりお待ちしております。
https://touki-samur-ai.com/contact/