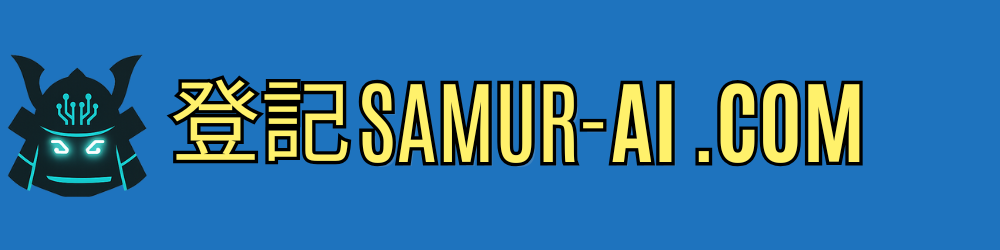AIは今後さらに進化し、2045年頃には人間の知能を超えるシンギュラリティ(技術的特異点)が訪れるとも言われています。
そんな未来では、単純作業や定型業務はほぼすべてAIに代替され、人間は創造性や共感力が求められる仕事に注力すると予想されていることでしょう。
士業においても、現場立会いや高度な判断を除く事務作業はほとんど自動化されるでしょう。
だからこそ今、「AIを使いこなせる士業」として準備を始めることが大切です。
AI活用スキルを身につけておけば、シンギュラリティ後の世界でも自身の専門性を発揮しつつAIと共存していけるでしょう。
本記事では、シンギュラリティが士業にもたらす可能性を俯瞰し、将来に向けてAI人材を育成する意義と具体的なステップを提案します。
「業務が楽になる」「新たな価値提供ができる」というモチベーションを原動力に、未来への一歩を踏み出しましょう。
2045年?AIと共存する未来をイメージする
2045年の士業業務はどのように変わっているのでしょうか?シンギュラリティとは?
ここでは、2045年の未来の士業を予測します。
シンギュラリティとは何か
シンギュラリティとはAIが人間の知能を超える転換点のことで、2045年頃に訪れる可能性があるとされています。
この時代になると、AIが自己進化しあらゆる知的作業を担うようになるため、社会・仕事の在り方が根本的に変化すると言われます。
単純作業やルーチンワークは完全にAIがこなすようになり、人間は創造性や人間同士のコミュニケーションが必要な分野に集中するようになるでしょう。
士業の仕事はどう変わる?
では、シンギュラリティの起こった未来では、土地家屋調査士や司法書士の業務はどう変わるのでしょうか。
図面作成・書類作成・申請といった定型部分はAIが瞬時に処理し、人間は難しい判断や顧客折衝にフォーカスする未来が想像できます。
例えば登記のオンライン申請はAIエージェントが自動対応し、士業者はクライアントへのコンサルティング(「このケースではどうすべきか」等)のみに時間を割く、といったイメージです。
極端に言えば、「AIを使いこなせる専門家だけが生き残る」とも予測されます。
裏を返せば、今からAI活用スキルを磨いておけば将来も必要とされる存在になれるということです。
「AIでは代替しにくい仕事」に注力するために
とはいえ、シンギュラリティは突然起こるわけでなく、その日までAIによる様々な変革が発生します。
AIを震源とする変化の時代に、土地家屋調査士・司法書士はどんな仕事をするべきでしょうか?
ここではAIが台頭しても変わらない土地家屋調査士・司法書士の強み、「AIでは代替しにくい仕事」について解説します。
土地家屋調査士の強み
幸いなことに、土地家屋調査士には測量や現地立会いなど物理的・対人的な現場業務があります。
AIやソフトウェアだけでは完結しないこうした業務は、シンギュラリティが来てもすぐには代替されにくい領域です。
実際、AIは文章生成やデータ処理は得意でも、現場で杭を打ったり隣地所有者と直接交渉したりといった作業はできません。
もちろん、鹿島建設が開発した自動施工システム「クワッドアクセル」のように、重機をAIで制御して、無人作業を実現している例もあります。
しかし、人の感情を伴う(特に理不尽にキレる方、何をしても連絡をくれない方、話は聞くけど「ハンコは押さない」と決めている方など・・・)隣地所有者との折衝は、感情を理解できないAIには難しいでしょう。
杭設置や測量作業はいつかAIが行うかもしれませんが、オペレーター・最終決裁者としての土地家屋調査士の役割は残ります。
司法書士の強み
同様に司法書士でも、家族信託や企業法務における高度な相談業務や、依頼者との信頼関係構築はAIには代替困難です。
AI時代でも人間ならではの判断力や共感力が求められる場面は必ず残ります。
言い換えれば、それ以外の反復事務はどんどんAIに任せ、人間は人間ならではの判断力や共感力が求められる高度業務にエネルギーを集中できる体制を整えることが、生き残るカギになります。
AI人材育成が不可欠に:スキル習得のススメ
何でもAIが代替してくれるとは言っても、常に学び続ける姿勢は必要です。
AIはあくまで「手段(ツール)」であり、AIを使いこなす人間も成長しなければなりません。
常に学び続ける姿勢が武器に
シンギュラリティ時代を迎えるにあたり、新しい技術やスキルを学び続ける姿勢が不可欠です。
AIに置き換えられやすい領域とそうでない領域の違いを理解し、AIを道具として使いこなす技術を身につけた士業は、将来にわたって価値を提供し続けられます。
具体的には、ChatGPTなどの生成AIの使い方だけでなく、自事務所向けにカスタマイズしたAIツールの開発・運用方法、データセキュリティに関する知識なども求められるでしょう。
こうしたスキルを社員全員で底上げしていくことが、将来のAI体制づくりに繋がります。
AI研修・情報収集の場を活用
幸い現在では士業向けのAI活用セミナーや研修講座も増えてきました。
社内で勉強会を開いたり、若手に最新ツールの情報収集を任せたりするのも有効です。
AI人材を育成することは将来への投資であり、特にベテラン士業者は「自分は詳しくないから」と敬遠せず、率先して学ぶ姿勢を見せることが大切です。
上司自身がAIに明るくなることで、部下も安心して習得に取り組めます。
また外部の専門家に相談し、自事務所に合ったAI導入プランを設計してもらうのも近道です。
専門家の支援を得れば、闇雲にツールを試すのではなく効果の高い施策から着手できるでしょう。
「AIを使える士業」であること自体が強みになる
「AIを使える士業」であることは、それ自体が「強み」といえる時代になりつつあります。
理由は大きく2つです。
- AI活用による差別化
- 新サービス創出のチャンス
それぞれについて、詳しく解説します。
AI活用による差別化
AI全盛の時代には、AIを活用できるか否かが士業者間の差別化要因にもなり得ます。
例えば、ある司法書士事務所がAI駆使による迅速な書類作成と情報提供で「対応が早く正確」と評判になれば、顧客にとっての魅力の一つとなります。
また、採用においても応募者が選ぶのは、どちらの事務所でしょう?
- 登記業務を昔ながらのやり方でこなす、ベテラン事務所
- 事務所用のカスタマイズされたAIを使ってルーティン作業や定型業務はAIにお任せ、従業員は内容のチェックとお客様対応に集中する、AI活用事務所
もちろん、どちらにも魅力はあります。
前者であれば登記の実務を一気通貫で覚えることができますし、後者であればコスパ・タイパを重視する人たちには響くでしょう。
しかし、AIが世間の仕事に浸透すればするほど、「AIにできる仕事を何でやらなきゃいけないの?」といった人が増えることは考えられます。
これはパソコンが一般社会に普及した時も同様で、1990年代後半~2000年代前半にはタイピング・そろばん(電卓)がパソコンに集約され、今ではパソコンの無い会社は存在しないのではないでしょうか。
新サービス創出のチャンス
AIを使いこなす中で、新たなサービスのアイデアも生まれます。
例えば、膨大な判例データを分析してアドバイスするコンサル業務や、測量データをAI解析して土地利用プランを提案するサービスなど、従来はなかった付加価値提供が可能になるかもしれません。
AIを恐れるのではなく味方につけることで、士業のビジネスチャンスはかえって広がる可能性もあります。
未来に向けてポジティブに捉え、チャレンジ精神を持って臨みたいところです。
このように、「AIが使える士業」であることはビジネスのあらゆる面で、アピールポイントにもなりうるのです。
将来、依頼者側も「この事務所は最新技術に対応していそうだ」と判断材料にするかもしれません。
今のうちからAI活用力を高め、テクノロジーにも強い専門家というブランディングを築いておきましょう。
まとめ:未来への一歩を踏み出そう
映画「ターミネーター」などのように、AIvs人類といった構図のシンギュラリティをイメージしていた方、この記事を読んでどう感じたでしょうか?
ご紹介した通り、AIはあくまで人工知能であり、シンギュラリティという言葉に漠然とした不安を感じる必要はありません。
大事なのは、来るべき未来に向けて備えることです。
本記事で述べたように、AIが高度化しても人間にしかできない領域は残りますし、そこに集中できるよう準備することで士業として生き残り、発展することが可能です。
「業務が楽になる」「将来性のあるスキルを身につけられる」という前向きな動機を持って、ぜひ今日からAI活用の第一歩を踏み出してみてください。
例えばChatGPTに簡単な質問を投げることからでも構いません。その小さな一歩が、5年10年後の大きな差となって現れるはずです。
登記事務所15年勤務の経験を持つ、AIプロとともに未来戦略を考えませんか?
AI時代に向けた備えは、一人で悩むより専門家の力を借りるのが確実です。
建物表題登記や地目変更、相続登記はシンプルなものであればネットで調べて本人申請ができるかもしれませんが、自分でやるよりも、その道のプロである土地家屋調査士・司法書士へ依頼した方がスムーズで確実ですよね。
これは、AIに関しても同じことが言えます。
「ウチの事務所でもAI導入しようか迷ってるけど、必要かどうか分からない」 そう思われた方は、まずはお気軽にご相談ください。(相談無料、オンライン対応) AI導入の要否、活用方針まで、御事務所の状況に合わせて具体的にアドバイスいたします。筆者(AIの杜さいた代表 岡田拓朗)は登記業界で15年、測量(確定測量、現況測量、ドローン測量、3D測量)、登記(表示・権利※相続)、許可(市街化調整区域の開発許可、農地法許可)の実務経験を有しています。
また、AIは2022年より活用しており、現在は土地家屋調査士・司法書士事務所のAI導入コンサルティングを行っており、実務経験を活かし、現場目線に立ったAI活用の伴走支援が可能です。
今まで培った経験と最新テクノロジーへの知識を融合し、皆様の事務所の未来戦略づくりを全力でお手伝いいたします。
「AIが使える士業」として一緒に次世代への一歩を踏み出しましょう!