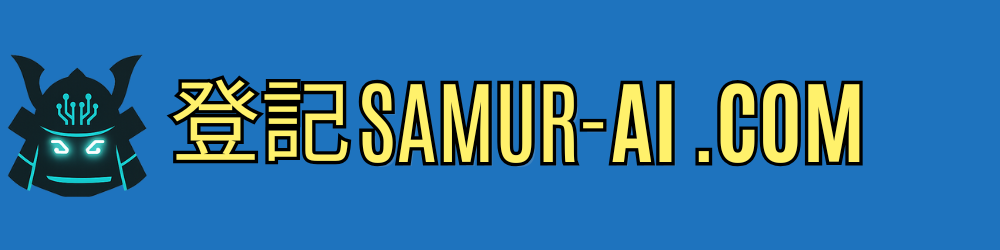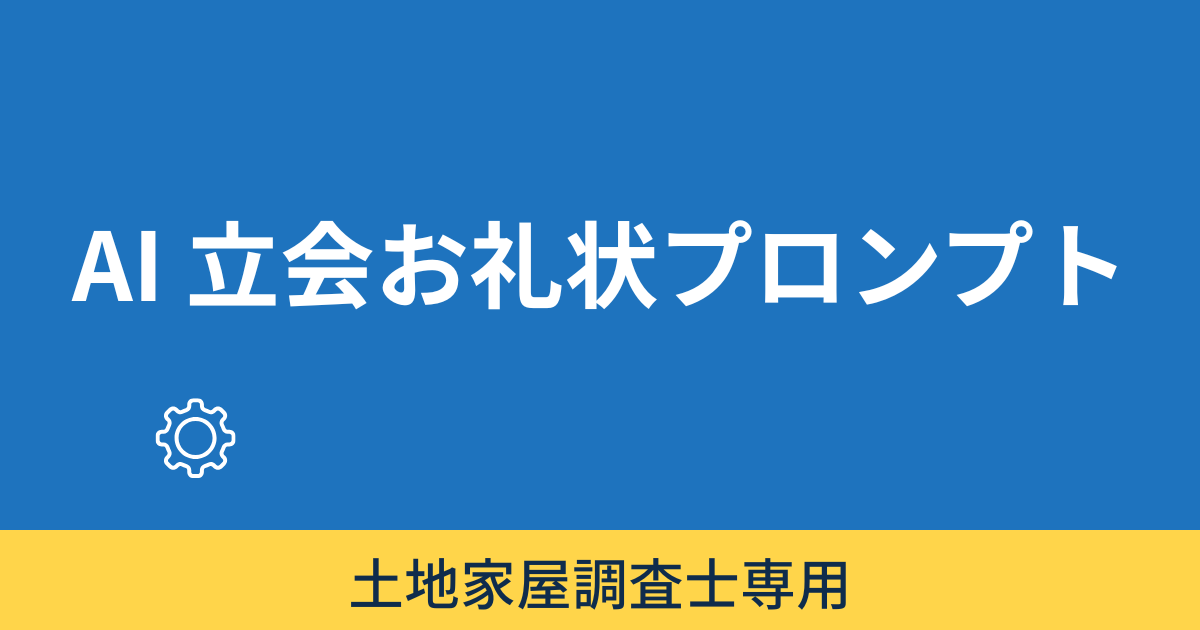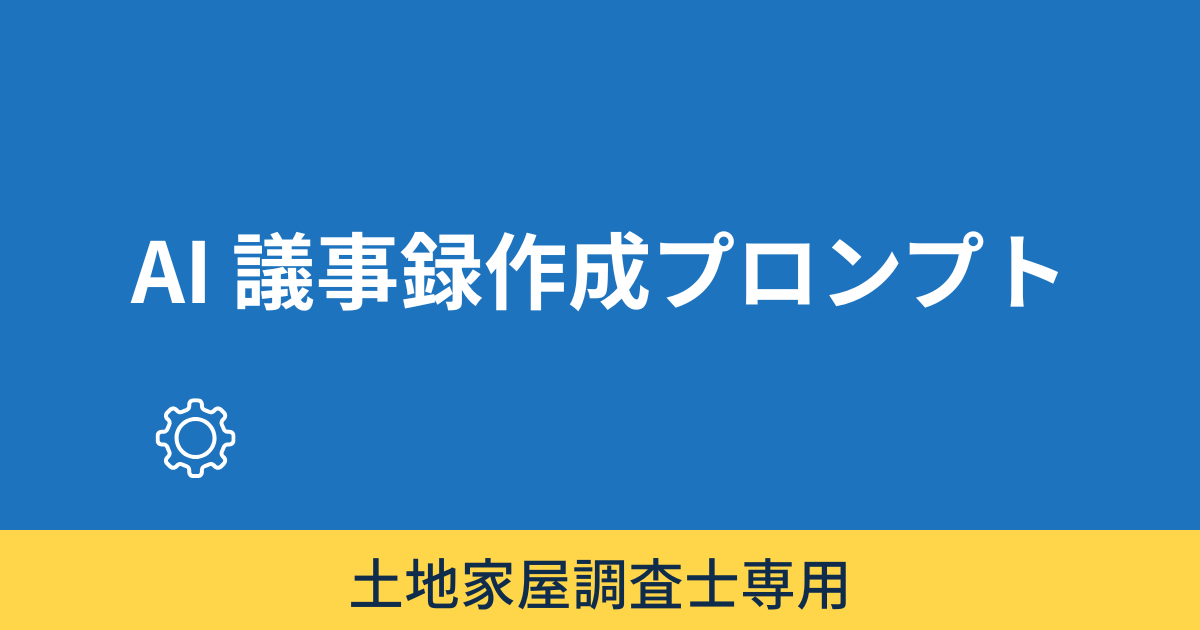第1部で、AIを「士業の仕事を奪う脅威」ではなく、現実的に“タスクを任せるパートナー”にしていくという発想の転換を確認しました。
本記事では、このパートナーであるAIを、土地家屋調査士・司法書士の現場で実際に役立つ“具体的な使いどころ”として、すぐ始められる順に整理してお届けします。
結論から申し上げると、登記事務所におけるAI活用は、「汎用(はんよう)×定型業務」から着手し、「登記特化×ひな型化」へと段階的に広げていくのが最も失敗の少ない王道です。
まずは社内文書、送付状、業務知識の整備(ノウハウ)といった共通業務のAI化を行い、次に隣地対応、境界関連文書、報告書といった専門業務へと展開していきましょう。
大切なのは、“全部を一度に”ではなく、“できるところから”試していくことです。
ステップ1:今日からできる―「汎用×定型」をAIに任せる
まずは、専門知識が少なくても、AIが持つ「文章作成能力」や「要約能力」を活かせる業務から着手します。
隣地挨拶状・各種送付状の下書き作成
測量前後の隣地挨拶状、委任状、見積、納品、請求といった各種送付状は、AIに以下の情報だけを渡せば数十秒で高品質な下書きが作成できます。
- 渡す情報:ひな型と条件(宛名、地番、期日、注意書きなど)
- 得られる成果:文面の丁寧さ、誤字脱字チェック、差し込み作業の自動化
「手紙の文章を考えるのにいつも時間がかかる」「ネットで探した例文を毎回コピペしている」という方は、まずこの定型業務のAI化を試してみてください。
「録音→文字起こし→書面化」:立会メモ・会議記録・作業報告
打合せや会議の後に、疲れた状態で議事録作成をするのは大変です。
しかし、AIを使えば録音以外はすべて代行してくれるため、議事録や立会メモの“使える初稿”を短時間で作れます。
【活用イメージ】
- 録音・文字起こし: ICレコーダーや専用アプリ(例:YYシステム※月80時間まで無料)で会話を録音し、テキスト化する。
- AIに書面化を指示: 文字起こしされたテキストをChatGPTなどのAIに渡し、「箇条書きでまとめて」「日付・案件名を先頭に」といった仕上げ方の指示を一言添える。
清書にかけていた時間を大幅に短縮し、すぐに次の業務に集中できます。
(注意:ChatGPTは文字起こし自体は苦手なため、別途文字起こしツールを使いましょう)
所内Q&A(知識・ノウハウ)は自分専用のAI(カスタムGPT)で“ベテランの知恵”を即時共有
「このケースの流れは?」「過去の類似事例は?」といった日常の疑問に即答する、事務所専用のAI(カスタムGPT)を所内に用意します。
※カスタムGPTはChatGPT有料版のみで作成できる機能です。ただし、カスタムGPTの利用は無料版でも可能です
社内マニュアルやチェックリスト、よくある質問(FAQ)を短い文章に分割してAIに読み込ませておくと、以下のメリットがあります。
- ベテランへの簡単な質問が激減
- 教育の平準化と応答スピードの底上げ
- 標準回答の初稿+参照元をAIが回答
ベテランの経験(属人知)を所員全体で共有できる、非常に強力な仕組みです。
「ウチの事務所でもAI導入しようか迷ってるけど、必要かどうか分からない」 そう思われた方は、まずはお気軽にご相談ください。(相談無料、オンライン対応) AI導入の要否、活用方針まで、御事務所の状況に合わせて具体的にアドバイスいたします。ステップ2:登記事務所“ならでは”の書面を賢くひな型化
ステップ1でAIに慣れたら、次は専門性の高い書面のひな型化を進めます。
境界確認書・越境物確認書・経緯書の下書き生成
ご自身の事務所の過去資料に合わせて語彙や条項のひな型をAIに事前学習させておきます。
その後は、案件の情報(当事者、地番、境界点、特記事項など)を入力するだけで、初稿を生成可能です。
- メリット: ゼロからの起草時間を短縮し、言い回しと体裁を所内で統一できるため、チェックの手間も軽減されます。
- 注意点: AIが出すのはあくまで下書きです。最終確認・法的判断は人の責任で必ず行ってください。
立会用説明資料・完了報告の“体裁整え”を自動化
現場写真や簡易図、要点メモをAIに渡し、「お客様説明用に見出し付きで整形」と指示を出すだけで、AIが見出し、箇条書き、注意喚起を付けた説明資料の素案を数分で返します。
資料体裁の均一化、説明の抜け漏れ低減、配布までの時間短縮といった効果が見込めます。
ステップ3:所内ルール周知・新人教育を“回る仕組み”に
AIを所内の知識基盤として活用することで、事務所の基盤を安定させることができます。
所内ルールの周知・Q&A化(更新がラクな運用)
所内規程やチェックリストを小さなデータ単位に分割してAIに読み込ませ、「検索→即答→出典提示」の動線を整えます。
変更があれば、該当データだけを差し替える運用が可能です。
- 効果: 最新ルールを全員が瞬時に参照でき、ヒューマンエラーを抑制します。
新人教育の立ち上げ:段階学習+演習+ふり返りの自動化
新人向けに段階別の学習ステップ(例:挨拶状→立会補助→報告書下書き)を用意し、各ステップでAIが小テストやチェックリストを自動生成します。
- 効果: 育成の標準化、進捗の見える化、ベテランの負担軽減。「まずはAIに聞く」という習慣が定着すれば、自律的な学習を促せます。
実装のコツ(セキュリティと運用)
AI活用を成功させるための重要なポイントです。
- データの扱い:
- 顧客名・取引先情報などの機密情報は、必ず業務向けの環境(ChatGPT Businessなど)で取り扱います
- 業務データを学習に使わない設定、権限管理、暗号化を前提としましょう
- 社外向けAIを使う場合は、機微情報を入力しないという運用ルールを徹底します
- ヒューマンエラー(メール・FAXの誤送信、書類の紛失等)にも注意しましょう。
AIデータの流出を防いでも、人間のミスがあるとセキュリティ事故が起こってしまいます
- “そのまま提出”は禁物:
- AIが出すのはあくまで下書きです。提出前には必ず資格者が責任を持って確認(最終確認・法的判断)を行ってください。
- 所長(または上長)がチェックするシステムも確立しましょう
- はじめは範囲限定:
- 隣地挨拶状、各種送付状、所内Q&A、音声起こしの4点セットから着手し、成果を確認してから段階的に拡大するのが賢明です。
まとめ:まず“書く”と“周知”の肩代わりから
登記事務所のAI活用は、書面作成、所内Q&A、音声→書面化、新人教育といった分野で確実に時間を作り出し、品質を平準化します。
現場は人、書面はAI――この分業こそが、事務所全体の処理量とお客様満足度を底上げする鍵です。
第3部では、シンギュラリティを見据えたAI人材育成と未来の事務所設計をご提案します。まずは明日から回せる一手を、所内でぜひ試してみてください。
(第3部はこちら↓)
無料相談(AI導入・所内運用設計)
筆者は登記事務所実務15年の経験があり、現場から書面運用の細やかなニュアンスまで把握しています。
「声で説明→書面化」「所内Q&Aの回し方」「ひな型の作り方」など、現場目線での現実解で伴走が可能です。
「まずどこから始めると最短で効果が出るか」を一緒に設計いたしますので、お気軽に無料相談へどうぞ。