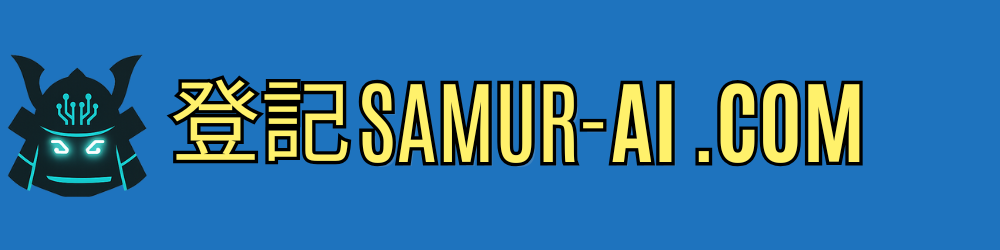「確定測量の仕事が多いのに、人手が足りない…」
「このままだと、いつか仕事がAIに奪われるのでは?」
もしあなたが今、そんな漠然とした不安を感じているなら、ご安心ください。
2022年末にChatGPTが登場して以来、士業業界では「AIが弁護士や税理士などの専門職をすべて置き換えるのでは?」という声が大きく報じられました。
しかし、4年経ってその見方は現実的な路線に移行しています。
その現実的な路線とは、「AIに任せられるのは定型的・細分化された業務だけで、人間にしかできない業務に専門家は特化していく」という方向性です。
本記事(全3部)では、こうしたAI時代の士業の役割変化を解説し、土地家屋調査士・司法書士がAIを導入する意義を考察します。
第1部の今回は、AI活用が進む他士業の事例にも触れ、読者が「AI=脅威」ではなく「AI=業務効率化の味方」と捉えられるよう現状の潮流を示します。
ChatGPT登場当初の衝撃
AI代替の不安が広まった背景
2022年末にChatGPTが公開されるや、AIの高度な文章作成能力や情報整理能力に社会全体が衝撃を受けました。
このインパクトは、2015年にオックスフォード大学と野村総合研究所が共同で発表した研究結果を再注目させるきっかけとなりました 。
特に注目すべきは、この研究で代替リスクが高いとされた職業の多くがいわゆる「現場作業」であった点です 。
具体的には、 測量士、建設作業員、機械木工、ビル清掃員などがAIやロボットに代替される職業とされました。
参考:日本の労働人口の49%が人工知能やロボット等で代替可能に(株式会社野村総合研究所)より
この結果から、弁護士や会計士といった専門知識を要する士業を含む「ホワイトカラー」の仕事は、AIによる代替が難しいと考えられていました 。
しかし、現在ではこの見解は逆転しています。
ペン・ワートン・バジェット・モデルの分析によれば、生成AIの影響は、多くの肉体労働や個人的サービスを主とする低賃金の仕事よりも、高賃金・高学歴の「知識労働」の方が最も大きな影響(エクスポージャー)を受けるとされています 。
これは、AIが自然言語を理解し、複雑な知識作業を処理する能力を持つため、専門性の高いホワイトカラー業務ほどAIによる自動化が進んでいることを示唆しています 。
「AIが士業から仕事を奪う」は本当か?
確かにAIの進化で、契約書ドラフト作成や登記申請書の作成など定型業務の自動化は現実味を帯びています 。
その後の専門的な再検証により、AIは職業全体を置き換えるのではなく、個々の業務を構成する「タスク」を効率化するツールであるという見方が次第に強まっています 。
つまり、AIは士業のすべてを置き換える魔法ではなく、士業が担う業務の一部を効率化するツールだという認識が主流になってきたのです。
現実路線への転換:「人にしかできない業務」への特化
単純作業のAI化と専門家の役割再定義
現在では「AIに置き換えられる業務は任せ、人間は人間にしかできない高度業務に集中する」という方向性が業界の共通認識になりつつあります。
例えば、司法書士であれば標準的な登記書類作成は専用ソフトやAIが下書きを自動生成し、資格者は内容確認と法的判断に注力する、といった形です。
土地家屋調査士でも、境界確認の説明文や報告書ドラフト(下書き)はAIに任せ、資格者は現地立会いや最終的な境界判断に力を割く、といった住み分けが考えられます。
AIが代替しにくい業務の価値
数学者である新井紀子氏の著作や研究は、AIが「統計と確率」を駆使して「最も確からしい答え」を提示するに過ぎず、人間が持つ「意味を理解する」能力にはいまだ到達していないと指摘しています 。
法的判断の最終責任や、依頼者との信頼関係構築、そして隣地所有者との微妙な交渉など、「意味理解」や「共感力」、「知覚と操作」が求められる業務はAIには代替できません 。
AIはあくまで、専門家の仕事をより洗練させ、より付加価値の高い業務に集中できるようにするための「賢いアシスタント」なのです。
そのため、AIが浸透する今後においても、「境界立会」という土地家屋調査士のメイン業務はAIに代替されず、その価値は更に高まるでしょう。
まとめ
AIは脅威ではなく、あなたの業務を支えるパートナーです。
本記事では、AI登場当初の過度な不安から、現在主流となっている「AIを賢く活用する現実路線」への変化を見てきました。
ポイントは、AIは士業そのものを不要にするものではなく、士業の働き方をアップデートするツールだということです。
AIを取り入れることで、「仕事が奪われる」どころか、業務が洗練・効率化され、人間にしかできない付加価値提供に集中できるようになります。
この記事を読んでいる土地家屋調査士の皆さんは、「書類作成や事務作業はAIを補助的に使って効率化」した上で、今後も付加価値の高い「立会業務」や「境界の最終判断」に注力できる環境を整えましょう。
次の記事では、他士業での成功事例を踏まえ、実際に「土地家屋調査士・司法書士事務所の具体的業務でAIがどう活用できるか?」を紹介します。
「隣地挨拶状」「境界確認書」など登記事務所特有の業務でも、AIを使えば効率化できる場面があるのです。
AI導入のイメージをより具体的に掴んでいただくため、ぜひ記事②もあわせてお読みください。