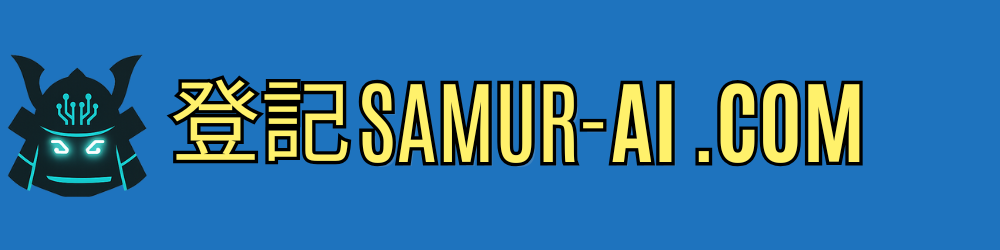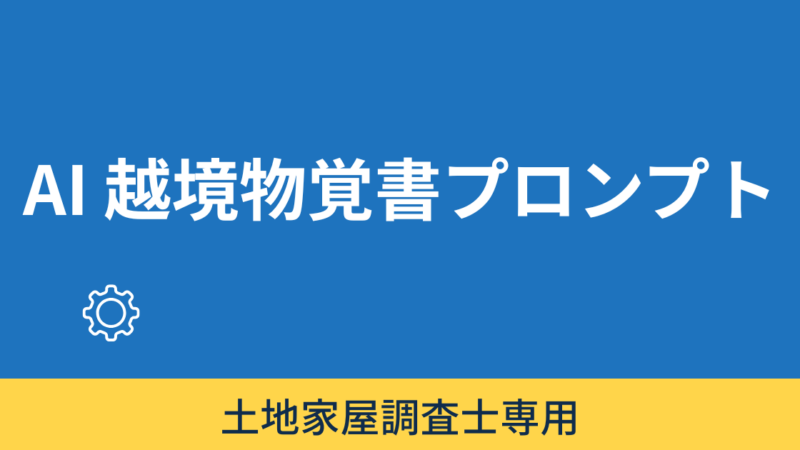
確定測量で「うっ」と来るのは越境物を発見した時ですね。
「数ミリだけど確実に出てる・・・」
「壊してくれないかなあ」
「地主さん、変なこと言いださないか心配」
「いや、出てない(←現実逃避)」
と色々な思いが巡ります。
境界立会で何とか双方に理解してもらった後、大変なことは「越境物の覚書」作成です。
これももちろん、ChatGPTで自動作成可能です。
すぐ使えるプロンプト(越境物覚書)
すぐにコピペして使いたい方は、下記のプロンプトをお手持ちのChatGPT(GoogleGeminiその他AIでも可能)に貼り付けてください。
※ただし、【隣地所有者】【依頼地所有者】欄は実際のお名前に入れ替えてください
目的:越境物覚書の起案(当事者表記は「甲」「乙」のみ)
役割:あなたは土地家屋調査士事務所に三〇年勤める熟達の補助者。
法務文書として整った、誤解のない日本語で起案します。出力要件:
– 文中の当事者は「甲」「乙」で統一し、実名・屋号は出力しない(内部参照:甲=佐藤一郎、乙=田中花子)。冒頭の定義文も含め、実名は表示しないこと。
– 数字は全角、日付は「〇月〇日」で表記。
– 「下記のひながた」に厳密に準拠し、越境物名・越境寸法(3cm)・処理方針・撤去期限(入力時のみ)を正しく反映。
– 第3条は処理方針に応じて該当ブロックのみ残し、他ブロックは削除する。削除後に生じる不要な空行は除去し、連続改行は一行に正規化して行間を詰めること。
– 書面体裁のみを出力する。(テンプレート)越境物覚書
【隣地所有者名】(以下、「甲」という)と、【依頼地所有者名】(以下、「乙」という)は、双方が所有する土地境界上の越境物について、以下のとおり合意した。第1条
甲・乙は、甲所有の越境物(ブロック塀の基礎)が、別紙確認図のとおり、乙所有の土地の境界線を越えて存在していること、ならびに越境寸法が概ね 3cm であることを相互確認した。第2条
乙は、甲所有の越境物について、建て替えや改築等で現状変更しない限り、撤去請求をしないものとし、現状のまま所有・使用することを承認する。第3条
甲は、甲所有の越境物について、将来に建て替えや改築等を行う際には、自己の責任と費用負担において越境物を撤去し、越境状態の解消を図るとともに、越境部分の乙所有地について時効の援用等による所有権を主張しないものとする。第4条
甲・乙は、所有地を第三者に譲渡する際に、本覚書の権利・義務を当該譲受人に対して継承させるものとする。以上、本覚書の成立を証するため、本書二通を作成し、甲乙各自署名押印のうえ、各一通を保有する。
令和 年 月 日
(甲)
住 所 ___________________氏 名 ___________________ ㊞
(乙)
住 所 ___________________氏 名 ___________________ ㊞
【厳守事項】
・当事者表記は「甲」「乙」に統一すること(氏名・屋号は出力しない)。
・数字は全角、日付は和文様式(令和〇年〇月〇日)。
・条番号は通し番号で重複・欠落がないこと。
・別紙確認図への言及を残すこと。
・冗長な修辞を避け、簡潔・明瞭に記載すること。
自分でプロンプトを作る
しっかりとした指示をしたい方は、下記のメーカーで作成したプロンプトを使い、越境物覚書をChatGPTでサッと書いてしまいましょう。
越境物覚書作成用プロンプトメーカー
完成文はそのまま、ChatGPTに貼り付けられます。
プロンプト使用時の注意点
AIの回答にはハルシネーション(事実と異なる「もっともらしい」嘘)などが含まれるので、プロンプトを工夫しても100%の正確性は担保できません。
特に、土地家屋調査士や司法書士など国家資格者からの書面であれば、誤情報であったとしても「そうなの?」とそのまま進んでしまい、後で大問題になる恐れがあります。
AIを使う場合には、下記のポイントに注意しましょう。
- AIの回答は人の目で必ずチェックする:生成AIで作ったものでも最終的な責任は、書類を作成した資格者が負うことになります。必ず人の目で最終チェックをしましょう。
- 最新情報を必ずチェックする:AIはネット上にある情報を基に生成しており、情報が古い、法改正を知らない、誤情報を基にしている、といったリスクがあります。法改正・新制度は、e-Gov(法令検索)や政府広報オンラインなどの公的サイトでチェックしましょう。)
- 機密情報は最低限に:生成AIに入力したデータは機械学習に使われる可能性があります。オプトアウト(学習させない)設定の利用、顧客情報や機密情報の入力は最低限にする、ChatGPT Team(法人向け2アカウント以上※デフォルトでオプトアウト設定)などで対策しておきましょう。